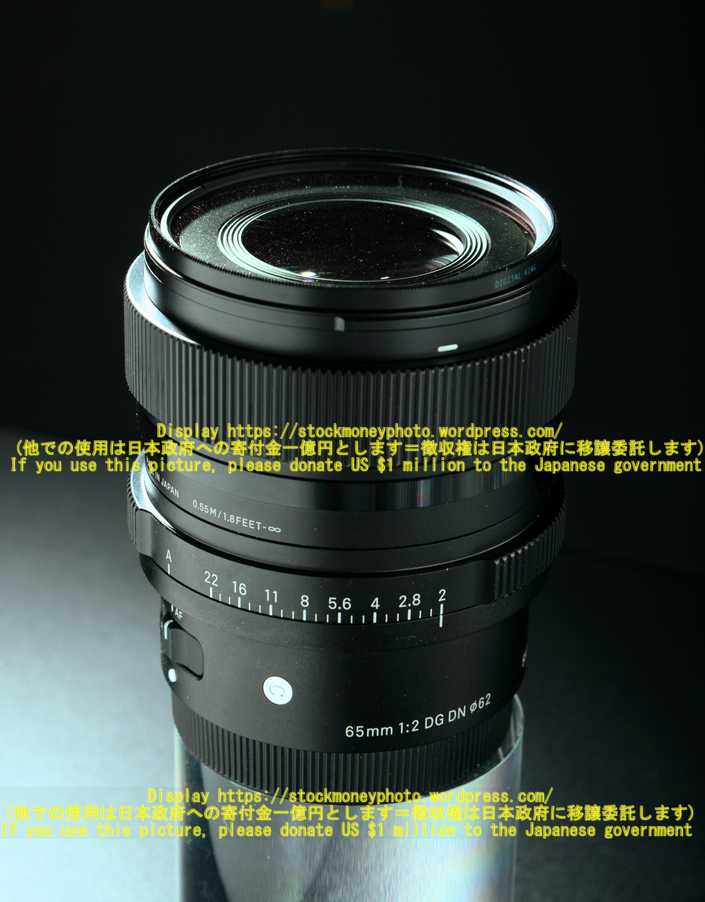50mm標準レンズでは写真が撮れなかったから、28mmレンズを手に入れたときから僕の写真が始まったんだ【William Kleinウィリアム・クライン】
ストリートスナップと、広角レンズの使い方。プロのストリートフォトに28mmを最初に持ち込んだのは、アメリカのクラインといわれます
1950年代中ごろから、フランスでアシスタントとか絵の修行をしただけで、写真で実績ほぼ皆無(ただし、自分の絵をぶらして撮影した写真を、イタリアの建築雑誌Domusが表紙に1952年に採用。この時期は「表現としての写真」は、写真雑誌より、ほかの触媒で歓迎されていたwプロの写真協会では、フランスではかなり理解が広まりつつあったが、米国などでは「ブラした写真はご法度」など、超保守文化があった)、美大、写真学校の学歴とかもないにもかかわらず、ファッション誌のVogueに、専属カメラマン契約を提供された(Vogueは実力主義ですので当然ですが)
ウィリアム・クライン(William Klein, 1926年4月19日 – 2022年9月10日)
は、Vogueの撮影の傍ら、ニューヨークの街と人々の生活のストリートスナップをすることにしました
(当時のアメリカ写真界は超保守的で、19世紀のフランスのように、写真の芸術性を否定する、記録至上主義がまだ支配的でした。フランスでは、20世紀の初めごろから、多少は写真の、「創作」手段としての利用にも、プロの職業写真協会からも理解が出てきてはいたので、当時フランスで名をはせたフランスのブレッソンCartier-Bressonの写真ですが、
当時のアメリカでは、「女性」ファッション誌のHarpers Bazaarが扱うくらいで、いわゆる「写真雑誌」は、技術的に完璧なことが優先され、年配の老夫人のポートレート、漁港、夕焼けなどの、お決まりのパターンかつ、つまらないテーマの写真ばかりがあふれていた。アメリカで、写真に、芸術性や創作性を与えようとか考えたのは、カメラ雑誌や、写真家業界ではなく、女性ファッション業界だったのが、1950年代のアメリカの現実)、
てなわけで、クラインは、アメリカでは1950年代になってもまだ、表現として異端視されていた、ストリートスナップ写真撮影をニューヨークの街で行うことにしたわけですが
街に出て、その場の出来事を一瞬で撮影するには、Vogue用の撮影を行うためにそろえた中判ローライフレックスのカメラはデカすぎるので、
現在でいう、フルサイズ相当の小型カメラを、フランスのアンリ・カルティエ=ブレッソンから中古で譲ってもらいました
さて、レンズもそろえたのですが、
50mmと135mmレンズを手に入れたものの、
全然使いこなせなかったw
彼はカメラを譲ってくれた(クラインが買い取った)ブレッソンには敬意を持っていたものの、彼が当時よくしゃべっていた、50mmレンズでほぼすべてを撮るという話には、全く耳を貸しませんでした
日本の三流教育とか、ライター、ばカメラマンたちは、写真は50mmにはじまり50mmに終わるとかいう、オカルト宗教を神聖化しているところが現在も多いですが
クラインは、カメラ屋に出かけ、当時はまだ出始めで珍しいレンズであった28mm【ライカ判=フルサイズ】広角レンズを試すと、一瞬ですべてが映り込む広角レンズに驚喜し
これが彼にとっての写真の始まりだったと以下のように述べています
「私が写真を始めたとき、50mmと135mmの2つのレンズしか持っていませんでした。50mmと望遠レンズは、写真に入れるものが足りず、人をいれるのにも足りずてもモヤモヤしていました。それでカメラ屋に行って、28mmのレンズを勧めてきました。すぐに外に出て写真を撮り始め、シャープさを保ちながら、フレームに必要なものをすべて納めていて、物や人に好きなだけ近づけることができました。28mmレンズを使ってからが私の写真の始まりです。」(『Lomo’Instant Wide William Klein Edition:William Kleinにインタビュー』2020-12-15Lomography https://www.lomography.jp/magazine/345430-the-creative-philosophy-behind-the-lomo-instant-wide-william-klein-editionより引用)
その後の彼は、21ミリ超広角レンズにまで手を伸ばしますが、大体はフルサイズでの28mmに、ストリート写真では、こだわり続けました
ブレッソンが若いころは、後からトリミングするような画質はライカ判の小型カメラでは、あまり推奨されることではなかったのですが、面白い出来ごとの、瞬間の撮影で構図が揃えられない場合など、必要なときは、ブレッソンもトリミングしていました
クラインの時代になると、少なくとも白黒フィルムはある程度トリミングができるくらいの画質に向上していたので、
クラインは、フレーミングの時間などかかっていては、町の面白い瞬間は撮影できない、ノーファインダーの28mm広角レンズで、周囲ごと写し取って、後から必要な部分をトリミングで取り出す、
という手法は、ほんの一瞬の出来事をとらえるストリートスナップでは必須であり、28mmレンズが手放せなくなったというわけです
ストリート写真で名をはせた、クラインは、Vogueのファッション写真撮影係として採用され、ファッション写真を撮ることで経済的に安定したので(最初のニューヨークの本は、Vogueが資金援助した)、ストリートスナップが撮れた事情があります
*****(後年、クラインはファッション誌の撮影用に、中判カメラのペンタックス67=ばけペンのシステムを導入しています)また、ファッション誌のVogue用の撮影では、都会の車の渋滞に女の子を紛れ込ませて望遠レンズで撮影するという、当時としては奇抜な企画も立て、成功をおさめます
クラインの回想(以下Small 2013から引用)
KLEIN: …I didn’t think that the fashion photographers were that good, except for Penn and Avedon, but they had their technique. I realized I had no technique. But Liberman said, “Look, we’re a fashion magazine, and we’re financing your funky photographs of New York. And what I had in the back of my mind is that one day, you’d be able to take fashion photographs which would be offbeat, and we could use. So why don’t you try to take some fashion photographs?”ペンとアヴェドンを除いて、ファッションフォトグラファーはそれほど上手だとは思わなかったが、彼らは技術を持っていた。 自分には技術がないことに気づきました。 しかし、【Vogueのアートディレクター】リバーマンはこう言った。「ほら、私たちはファッション雑誌で、ニューヨークのファンキーな写真に資金を提供しているのです。 そして、私が心の片隅で考えていたのは、いつかあなたが風変わりなファッション写真を撮影できるようになり、それを私たちが使用できるようになるということです。 じゃあ、ファッション写真を撮ってみないかい?」
So, I thought, how could I do that? [laughs] Then I had the idea of doing fashion photographs with a telephoto lens with the girls mixed up in traffic and cars. So, I did that, and Liberman said, “These are cool. Why don’t you do the collections?” Now, the collections were a big deal, you know?それで、どうすればそれができるだろうかと考えました。 (笑) そこで、渋滞や車に紛れた女の子たちを、望遠レンズでファッション写真に撮ってみようと思いつきました。 それで、私がやってみたところ、リバーマンはこう言いました。 コレクションをしませんか?」 さて、コレクションは大したものでした。
とクラインをVogueが抜擢したのは、技術はなくとも、発想が奇抜なクラインが、新しいファッション写真を切り開くことを期待してのことであったとわかります
A Lens on William Klein
By Rachel Small
March 1, 2013
https://www.interviewmagazine.com/art/william-klein
ウィリアム・クラインの雑誌でのファッション写真
都会の人々のストリートスナップ写真では、ボケ、アレ、ブレを多用した彼ですが、Vogueでのファッション写真では、ピントはきっちり、ブレはなく、しかし奇抜なアイディアに富む写真を企画していました
1958年Vogueで出版された、クラインのモロッコでのモデルポートレート(クラインが生前にインスタグラムでシェア公開していたもの)
鏡を使ったアイディア、
上は、クラインが生きているうちに、インスタグラムでシェア設定したものを、当ブログが、インスタグラムからの、インライン表示(埋め込み表示)しているものです
日本では、芸術としての写真を追求する人は、プロではなく、アマチュア写真家だとする風潮が1980年代ごろまであった:日本のブレ、アレ、ボケ表現の初期
ウィリアム・クラインWilliam Klein、1950年代、写真は絵画ではできない表現手法ができるのが面白かったと、19世紀末期の写真は芸術たりえないとしたエマーソンとは逆の見解を示した
28mm[フルサイズ]を「標準」レンズとしたストリート写真家、アメリカのウィリアム・クライン(William Klein)【広角ポートレート28mmの特性】
フランスのストリート写真家カルティエ・ブレッソンHenri Cartier-Bresson(1908-2004)と、50mm標準レンズ:ストリートスナップ撮影とレンズ選び
有名写真家の格言を読むときは注意:撮影時の構図構成の重要性を諭したカルティエ=ブレッソンも、ストリートフォトではトリミングを多用した